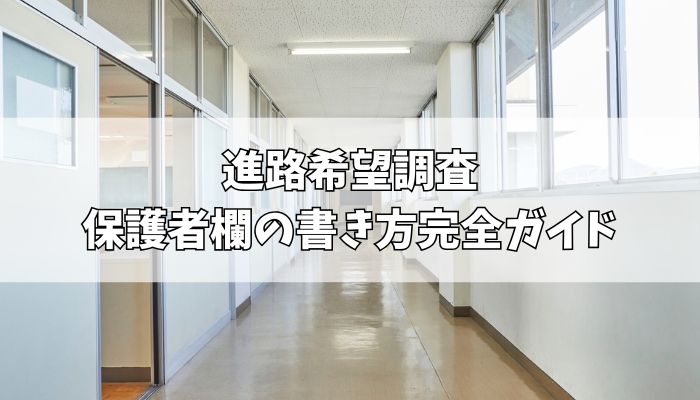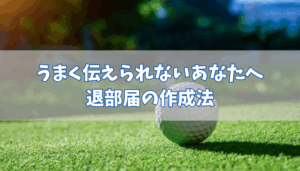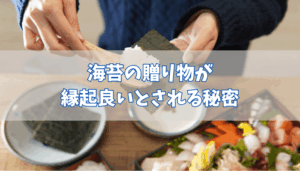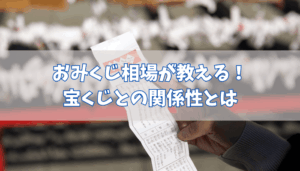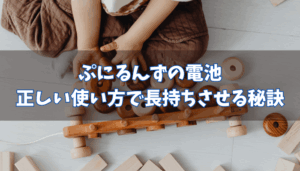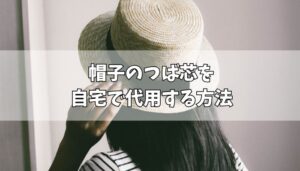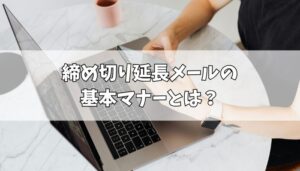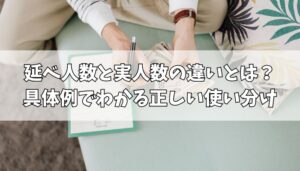中学生の進路希望調査で「保護者欄には何を書けばいいの?」と迷う方は多いです。
学校側は、家庭の考えを把握し、子どもに合った進路指導を行うために保護者の意見を求めています。
この記事では、進路希望調査の保護者欄にどのような内容を書けばよいのか、実際の例文を交えながら分かりやすく解説します。
「子どもの希望を尊重したいけど、親としての考えも伝えたい」「推薦入試を希望する場合はどう書く?」など、さまざまなケースに対応。
この記事を読めば、迷わず記入できるだけでなく、学校との信頼関係を築ける“伝わる保護者欄”が書けるようになります。
進路希望調査とは?保護者が理解しておきたい基本
この章では、進路希望調査の基本的な仕組みや目的について解説します。
学校がなぜこの調査を行うのかを理解することで、保護者としてどのように関わればよいかが明確になります。
進路希望調査の目的と学校での扱い
進路希望調査は、生徒の将来の方向性を早い段階で把握し、必要なサポートを行うために実施されるものです。
中学校では、生徒一人ひとりの希望進路を把握し、学力や適性、生活状況などを考慮して進路指導を行います。
つまり、進路希望調査は生徒の進路を決める“最初の一歩”であり、先生と家庭をつなぐ重要な資料です。
調査内容は担任の先生を中心に管理され、学年会議や進路指導会議で参考にされます。
特に高校受験を控える中学3年生の場合、この調査結果が志望校面談や三者面談の基礎資料となります。
| 目的 | 学校側の活用 |
|---|---|
| 生徒の希望進路を把握する | 進路指導や面談での参考にする |
| 家庭の考えを共有する | 家庭と学校の意見を調整する |
| 学力や適性との整合を確認する | 受験校・推薦校の提案を行う |
調査の時期と提出スケジュールの一般的な流れ
進路希望調査は、学校によって実施時期が異なりますが、一般的には中学3年生の4月・6月・9月・12月の4回程度行われます。
初回は「進路の方向性」を確認する目的で実施され、年末にかけて志望校や受験方法を確定していく流れです。
提出期限を守ることは非常に重要で、遅れると面談の予定や高校との調整に支障が出ることがあります。
提出が遅れると、推薦の準備や志望校調整が間に合わなくなるケースもあるため注意が必要です。
| 実施時期 | 目的 |
|---|---|
| 4月 | 進路への意識づけ、方向性の確認 |
| 6月 | 志望校の候補整理、学力との照合 |
| 9月 | 受験校の絞り込み、推薦候補の検討 |
| 12月 | 最終的な進路希望の確定 |
焦らず、段階的に考えを整理していくことが、親子ともに納得のいく進路選択につながります。
保護者欄には何を書く?基本の考え方

この章では、進路希望調査における「保護者欄」に何を書けばよいのか、その基本的な考え方を整理します。
先生がどんな情報を知りたいのかを理解しておくと、無理のない形で家庭の考えを伝えることができます。
学校が「保護者の意見」を求める理由
進路希望調査の保護者欄は、単に形式的に記入するためのものではありません。
学校側は、家庭がどのような考えで子どもの進路を考えているのかを知ることで、より適切な支援やアドバイスを行うことができます。
たとえば、家庭で「通学距離を重視したい」「経済的な理由で公立を希望したい」といった事情がある場合、それを先生が把握しておくことがとても重要です。
保護者欄は、家庭の意向を学校に正確に伝えるための“コミュニケーション欄”なのです。
この欄を通して、学校と家庭が同じ方向を向いて子どもの進路を考えることができます。
| 記入の目的 | 期待される効果 |
|---|---|
| 家庭の考えを共有する | 担任が生徒の背景を理解しやすくなる |
| 親子の話し合いのきっかけにする | 子どもが自分の考えを整理しやすくなる |
| 進路指導との連携を強化する | 先生からより具体的な提案を受けやすくなる |
親として書くべき内容と避けたい表現
保護者欄では、親の意見を率直に書くことが大切です。
ただし、感情的になったり、曖昧すぎたりすると、先生が意図を読み取りづらくなってしまいます。
基本的には次の3つのポイントを押さえると、読みやすく誠実な文章になります。
- ① 子どもの希望を尊重していることを伝える
- ② 家庭の状況や考え方を具体的に書く
- ③ 学校への協力的な姿勢を示す
たとえば、「親としては〇〇高校が合っていると思うが、子どもの意見を尊重したい」といった書き方は、保護者としての思いと支援姿勢をうまく両立しています。
避けたいのは、「まだ決まっていません」「よく分かりません」といった、情報が伝わらない書き方です。
現時点での考えを正直に書けば十分であり、完璧な答えを求める必要はありません。
大切なのは、「子どもをどう支えたいか」という姿勢を伝えることです。
| 良い記入例 | 避けたい記入例 |
|---|---|
| 子どもの希望を尊重しつつ、通学可能な範囲で検討しています。 | 特に考えていません。先生にお任せします。 |
| 家庭としても第一志望を応援し、必要なサポートをしていきたいと考えています。 | 本人に任せているので、意見はありません。 |
| 公立高校を第一志望としていますが、私立高校も併願予定です。 | どの学校でもいいと思います。 |
このように、保護者欄は“家庭の想いを伝える手紙”のようなものです。
短くても構いませんが、先生が状況を理解しやすいよう、背景や理由を一言添えるのが理想的です。
誠実に書かれた保護者欄は、先生からの信頼と丁寧な進路支援につながります。
進路希望調査の保護者欄|実用的な書き方ポイント
この章では、実際に保護者欄へ記入する際に意識したいポイントを紹介します。
書き方のコツを押さえることで、短い文章でもしっかりと想いが伝わる記入ができます。
子どもの希望と親の意見をどうまとめるか
進路希望調査で最も大切なのは、子どもの希望を尊重しながら、保護者としての意見をどう伝えるかです。
例えば、「子どもは〇〇高校を希望しているが、学力とのバランスを考えて〇〇高校も検討している」といった書き方が理想です。
これは、親が冷静に状況を見ていることを示しつつ、子どもの意志を否定しない表現になります。
“子どもの意見を尊重しながら、家庭としての考えを添える”ことが、最も信頼される書き方です。
| 記入例 | ポイント |
|---|---|
| 子どもの希望校を中心に検討していますが、学力や通学時間も考慮しています。 | 家庭の考えを補足しつつ、子どもの希望を優先している姿勢を示している。 |
| 本人の意思を尊重しつつ、相談しながら最適な進路を一緒に考えていきたいです。 | 親子の協力的な関係を伝える良い書き方。 |
進路変更があった場合の対応方法
「最初に書いた志望校から変わった」と心配する保護者も多いですが、それは珍しいことではありません。
中学3年生の1年間で、学力の伸びや興味の変化によって志望校が変わるのは自然なことです。
進路変更がある場合は、調査票にそのまま正直に記入し、必要に応じて担任の先生に相談すれば大丈夫です。
学校側も進路変更を前提にサポート体制を整えているため、ためらう必要はありません。
「以前は〇〇高校を希望していましたが、現在は□□高校を目指しています。」と書くだけでも十分です。
| 進路変更の理由例 | 書き方のヒント |
|---|---|
| 学力の変化 | 「成績の推移を見て、新たな学校を検討しています。」 |
| 興味・関心の変化 | 「子どもの関心が変わり、専門学科への進学を希望しています。」 |
| 通学・環境の考慮 | 「家庭の事情により、通学範囲を再検討しています。」 |
進路は一度決めたら終わりではなく、“変化していくもの”と考えることが大切です。
推薦入試を希望する場合の注意点
推薦入試を考えている場合、学校との情報共有が特に重要になります。
推薦には「一般推薦」と「特別推薦」があり、どちらも学校の推薦枠や条件が関係するため、早めに担任の先生と相談しておくことが必要です。
保護者欄では、「推薦を希望している」「必要な条件を確認している」といった姿勢を明記しましょう。
提出が遅れると推薦の手続きが間に合わないこともあるため、スケジュール管理も忘れずに。
| 推薦の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 一般推薦 | 成績や出席状況など、一定の基準を満たす生徒が対象。 |
| 特別推薦 | スポーツ・文化活動などで特技を持つ生徒が対象。 |
例文としては、次のように書くと丁寧です。
「息子は〇〇高校の推薦入試を希望しており、基準を満たせるよう努力しています。必要な手続きについて、先生からのご指導をお願いしたいと思います。」
推薦入試は家庭と学校の連携が成功のカギです。早めの相談と正確な記入を心がけましょう。
進路希望調査の保護者欄|ケース別の記入例

この章では、実際の記入をイメージしやすいように、さまざまな状況に応じた例文を紹介します。
家庭の事情や子どもの目標に合わせて、言葉を少し変えるだけで、より自然で伝わりやすい保護者欄に仕上がります。
通学範囲を考慮した場合の例文
共働きの家庭や、通学時間を重視したい場合に使える書き方です。
無理のない通学環境を希望している旨を、率直に伝えましょう。
| 例文 | ポイント |
|---|---|
| 両親ともに共働きのため、できるだけ自宅から通学しやすい範囲の高校を希望しています。子どももこの考えに賛同しており、〇〇高校または△△高校を検討しています。 | 家庭の事情を丁寧に説明しつつ、子どもの意見も尊重している。 |
通学面を重視する場合は、「家族全体の生活リズム」として伝えると理解されやすいです。
公立高校・私立高校を希望する場合の例文
公立高校を第一志望にする場合、家庭の事情や学費面の考え方を添えると説得力が増します。
私立高校を希望する場合は、教育環境や進学実績への理解を示すことがポイントです。
| 状況 | 例文 |
|---|---|
| 公立高校希望 | 経済的な事情もあり、公立高校への進学を希望しています。子どもとも十分に話し合い、第一志望は〇〇高校としています。私立高校も併願を検討中です。 |
| 私立高校希望 | 子どもは私立の〇〇高校に魅力を感じており、親としても学習環境を高く評価しています。学費面についても家庭で計画を立て、進学を応援したいと考えています。 |
「経済的な事情」や「家庭の方針」は遠慮せず書いて構いません。
それが学校にとって適切な支援を行うための大切な手がかりになります。
専門学科・推薦・就職など特別なケースの例文
専門学科への進学や推薦入試、または就職希望など、特別なケースでは「理由」と「支援姿勢」をしっかり書くことが大切です。
学校側は、動機の明確さや家庭の理解度を重視します。
| ケース | 例文 |
|---|---|
| 専門学科希望 | 子どもは将来デザイン関係の職業を希望しており、〇〇高校デザイン科を目指しています。家庭としてもこの方向性を支持し、受験に向けてサポートを続けていきたいと考えています。 |
| 推薦入試希望 | 息子は〇〇高校の特別推薦を希望しています。日々の学習と部活動の両立を意識して努力しており、家庭でも応援しています。必要な手続きについて先生のご指導をお願いしたいです。 |
| 就職希望 | 子どもは中学卒業後に地元企業での就職を希望しています。家庭としては進学も勧めていますが、本人の意思を尊重し、先生と相談しながら最適な道を探っていきたいと考えています。 |
これらの例文はあくまで参考です。
重要なのは、どのケースでも「子どもの意思」と「家庭の考え」を両方示すことです。
そのバランスこそが、学校との信頼関係を築く最も効果的な方法です。
子どもの進路に悩むときの親の対応
この章では、「子どもの進路が決まらない」「意見が合わない」といった保護者の悩みに寄り添いながら、適切な向き合い方を解説します。
焦らず、子どもの成長のペースに合わせて考えることが大切です。
進路が決まらないときの相談先
中学3年生の秋ごろになっても「まだ進路が決まらない」というケースは珍しくありません。
進路を選ぶことは、自分の将来を見つめる作業でもあるため、時間がかかるのは当然です。
そんなときは、一人で悩まず、まずは担任の先生に相談してみましょう。
担任の先生は、子どもの学力や性格をよく理解しており、最も現実的なアドバイスをくれる存在です。
また、進路指導担当の先生や、スクールカウンセラーに相談するのも効果的です。
第三者に話すことで、親子では見えなかった選択肢が見つかることもあります。
| 相談先 | 相談内容の例 |
|---|---|
| 担任の先生 | 成績や志望校の妥当性、推薦の可能性など |
| 進路指導の先生 | 学校ごとの特徴、受験制度、併願の仕方 |
| スクールカウンセラー | 子どもの気持ち、家庭での接し方、心理的サポート |
「まだ決まっていない」と伝えるのは恥ずかしいことではありません。
むしろ早い段階で相談するほど、先生は柔軟にサポートできます。
意見が食い違うときの話し合い方
親が「安全な選択」を望む一方で、子どもは「挑戦したい」と思うことがあります。
このように意見が食い違うのは自然なことです。
大切なのは、どちらかの考えを押しつけるのではなく、お互いの立場を理解し合うことです。
たとえば、家庭で次のような話し方を意識してみましょう。
- 「なぜその学校を選びたいのか」を子どもに丁寧に聞く
- 親の考えも“提案”として伝える(命令ではなく)
- 感情的にならず、情報を共有する
たとえ最初は平行線でも、子どもが親に自分の考えを話せる関係を保つことが何より大切です。
最終的に子どもが自分で決めた選択は、強いモチベーションにつながります。
| 親のNG対応 | 望ましい対応 |
|---|---|
| 「その学校は無理」「やめた方がいい」と否定する | 「どうしてその学校がいいと思うの?」と理由を聞く |
| 親の希望を押しつける | 家庭の事情を説明しながら話し合う |
| 話し合いを避ける | 定期的に時間を設けて意見交換する |
通信制高校など代替案の検討
子どもが「高校に行きたくない」と言う場合、焦らず選択肢を広げて考えましょう。
通信制高校や定時制高校など、さまざまな学び方があります。
通信制高校は、登校日が少なく、自分のペースで学べるのが特徴です。
勉強が苦手な子や、集団生活にストレスを感じる子に向いています。
高校に通う形は一つではありません。子どもに合った環境を探すことも、親の大切な役割です。
| 学校の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 全日制高校 | 一般的な学習スタイルで、進学実績も多い。 |
| 定時制高校 | 昼・夜の部があり、働きながら通うことも可能。 |
| 通信制高校 | 登校日が少なく、自分のペースで学べる。 |
子どもが進路に迷っているときこそ、親が“安心できる味方”であることを示すチャンスです。
「どうしたい?」と問いかける姿勢が、子どもを前向きにします。
まとめ|保護者欄は「子どもと学校をつなぐ大切な一文」

ここまで、進路希望調査の保護者欄について、基本の考え方から具体的な書き方、そして親としての向き合い方までを解説してきました。
最後に、保護者として心に留めておきたいポイントを整理します。
正直で前向きな記入が信頼関係を築く
保護者欄は、単なるアンケートではなく、先生と家庭をつなぐ大切な「対話の入り口」です。
形式的に書くよりも、今の気持ちを正直に書くことで、学校側は子どものサポートをより的確に行えます。
たとえ結論が出ていなくても、「迷っている」「相談したい」という一文で十分意味があります。
大切なのは、子どもの成長を見守る姿勢と、先生への信頼を言葉にすることです。
| 良い記入例 | 伝わるポイント |
|---|---|
| 子どもの希望を尊重しながら、現実的な選択を一緒に考えていきたいです。 | 親子の協力姿勢と柔軟さを示している。 |
| まだ具体的な志望校は決まっていませんが、担任の先生と相談しながら進めたいと思います。 | 不確定な状況でも前向きな姿勢を表現している。 |
進路希望調査を通して子どもの成長を支える
進路希望調査は、「子どもが自分の将来を考える練習の場」ともいえます。
親の役割は、答えを出すことではなく、子どもが自分の考えを言葉にできるよう支えることです。
保護者欄に書く言葉は、子どもへの信頼の表れでもあります。
迷いや不安があっても、親が「一緒に考えるよ」と伝えることで、子どもは安心して進路に向き合えるようになります。
| 親の支え方 | 具体的な行動 |
|---|---|
| 子どもの話をよく聞く | 否定せず、まずは「そう思うんだね」と受け止める。 |
| 情報を一緒に調べる | 志望校の資料を取り寄せたり、学校説明会に同行する。 |
| 学校と連携する | 担任に進路の方向性を相談し、支援方針を共有する。 |
最後にもう一度強調しておきたいのは、進路希望調査は“親子の共同作業”だということです。
完璧な答えを書く必要はありません。
今の気持ちを素直に記すことが、子どもの未来を支える最初の一歩になります。